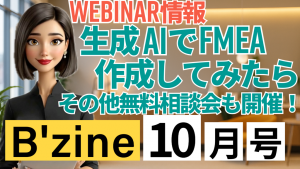B'zine
B’zine – 2025年10月号(Webinar開催~生成AIでFMEAを作成してみたら~など)を発行しました
10月下旬になり朝晩はめっきり肌寒くなりました。
秋の行楽シーズン到来ですが、山奥深い場所や人気のない場所への侵入や単独行動は控え、熊出没注意報にも十分注意して、紅葉狩りをお楽しみください。
B’zine 10月号を発行いたしました。
動画版(約3分)も公開していますので、弊社公式YouTubeより是非ご視聴ください。
B’zineは、1回/月のペースでの配信しています。ご興味のある方は、ここから登録をお願いいたします。
B’zine
ビジネスガレージ通信(2025年10月号)
- B’zine 10月号をお届けします。10月下旬になり朝晩はめっきり肌寒くなりました。秋の行楽シーズン到来ですが、山奥深い場所や人気のない場所への侵入や単独行動は控え、熊出没注意報にも十分注意して、紅葉狩りをお楽しみください。【今月のトピックス】
- イベント:第6回 ビジネスガレージオープンWebinar開催(11/26)
- コラム :無料相談会(ミニコンサル)11月開催
- コラム :使えるプロセス vs 使われないプロセス:決定的な違いと成功事例
- コラム :ソフトウェアテストのプロセス改善を支える国際標準 ~Test SPICE~
- コラム :「テスト頼み」からの脱却 ─ レビュー文化が品質を変える
【イベント】
- 2025年11月26日 Webinar ~生成AIでFMEAを作成してみたら~ のご案内
ChatGPTを活用することで、FMEAの作成期間とリソースを劇的に削減した事例をご紹介します
日時:2025/11/26(水) 16:00 – 16:50
お申込みはこちらから → https://www.bgarage.co.jp/news/1496/ - 無料相談会(ミニコンサル)11月開催のご案内
弊社では、皆様のお困りごとに対する相談会を実施しています。Automotive SPICE/プロセス改善/プロジェクト管理など、お気軽にご相談ください。
お申込みはこちらから → https://www.bgarage.co.jp/news/1494/ - 2026年1月 Webinar(予定): EARSを活用した要求の書き方
構文形式を利用することで、書き手と読み手の解釈不一致を防止する要求の文書化手法と事例をご紹介します。
【コラム】
- 使えるプロセス vs 使われないプロセス:決定的な違いと成功事例
プロセス改善は、こうした属人的な開発から脱却し、誰がやっても一定の品質・納期・コストを再現できる仕組みをつくるための重要な取り組みです。しかし近年、開発の複雑化や規格対応の厳格化により、品質問題や納期遅延のリスクはますます高まっています。その一方で、監査や認証取得を目的に整備された“形だけのプロセス”が現場で使われず、改善が止まってしまうケースが増えているのも事実です。良いプロセスも、現場で使われなければ意味がありません。では、なぜプロセスは使われなくなるのか?どうすれば現場で本当に役立つプロセスになるのか?
このコラムでは、私たちの現場支援の経験をもとに、成功のヒントをいくつかご紹介します。
詳細はこちら → https://www.bgarage.co.jp/news/1424/ - ソフトウェアテストのプロセス改善を支える国際標準 ~Test SPICE~
ソフトウェア開発において、テストは品質保証の要です。しかし、テスト活動そのものの成熟度やプロセス品質を体系的に評価・改善する枠組みは、長らく十分に整備されていませんでした。そこで登場したのが Test SPICEです。
Test SPICEは、ISO/IEC 330xxシリーズの一部として策定された、ソフトウェアテストに特化したプロセス評価モデルです。従来のSPICE(Software Process Improvement and Capability Determination)モデルをベースに、テスト活動の特性に合わせて設計されています。
「検証サービスプロバイダ」 に求められる組織能力を可視化し、プロセス改善による組織能力向上を図ることを目的としていますが、テスト資産の再利用や回帰テストの自動化など、ソフトウェア開発組織のテストプロセスの改善にも有益な内容になっています。
詳細はこちら → https://www.bgarage.co.jp/news/1464/ - 「テスト頼み」からの脱却 ─ レビュー文化が品質を変える
製品開発における品質保証は、テスト工程に偏りがちです。多くの組織では、テストで検出された不具合をもって品質を評価し、設計工程でのレビュー指摘は記録されない、あるいは品質活動の一部として認識されていないことがあります。しかし、品質は本当に“テストだけ”で保証できるのでしょうか?
テストは重要な工程ですが、あくまで後工程であり、設計段階での不具合をすべて検出できるわけではありません。特に組込み系開発では、タイミング依存や環境依存の不具合が多く、テストだけでは限界があります。設計段階での不具合を未然に防ぐには、レビューによる“作り込み”が不可欠です。
詳細はこちら → https://www.bgarage.co.jp/news/1453/